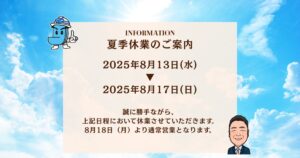解体工事における残置物トラブルを回避!無駄な費用を抑える適正処理ガイド

自宅や実家の解体、賃貸物件の退去時など、「残置物」の処理に悩む方は少なくありません。部屋に残された家具や家電、生活用品の山を前に、どこから手を付ければいいのか分からず、途方に暮れてしまうこともあるでしょう。
この記事では、残置物の適正な処理方法に加え、解体工事を円滑に、そして無駄なく進めるための具体的な対策を、岡山で解体工事を手掛けてきた日本クレストの知見に基づきご紹介します。適切な管理が、費用削減やトラブル回避、環境への配慮にもつながることをぜひ知っておいてください。
残置物とは?放置された「モノ」が生む問題
「残置物(ざんちぶつ)」とは、建物の中や敷地内に、以前の所有者や使用者が残した家具や家電、生活用品など、不要となった物品の総称です。解体工事だけでなく、不動産売買や賃貸物件の退去、遺品整理などの場面でもよく問題となります。
具体的には、以下のようなものが残置物として挙げられます。
| 大型家具 | タンス、ベッド、ソファ、机、椅子、衣装ケースなど。 |
| 家電製品 | 冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコン、電子レンジ、パソコンなど |
| 日用品 | 食器、衣類、本、雑誌、趣味の品、布団、プラスチック製品、小物など |
| その他 | 自転車、鉢植え、仏壇、位牌、アルバムなどの思い出の品 |
廃棄物の分類:一般廃棄物と産業廃棄物
残置物は、誰が処分するかによって「一般廃棄物」と「産業廃棄物」のいずれかに分類が変わり、それぞれ処理方法が異なります。
一般廃棄物
一般廃棄物とは、廃棄物処理法で規定された産業廃棄物以外の廃棄物のことで、主に家庭から排出されるゴミを指します。自分で処分する場合は、残置物も一般廃棄物として扱われます。
特徴
自治体のゴミ収集サービス(可燃ごみ、不燃ごみ)や粗大ごみ回収を利用して、無料かわずかな費用負担で処分できます。
具体例
雑誌、新聞、衣類、プラスチック製品、使わなくなった小物、小さな家具(椅子、テーブル、布団など)などが該当します。
産業廃棄物
産業廃棄物は、事業活動から排出された廃棄物で、廃棄物処理法で規定された20種類を指します。これには、紙屑、木屑、プラスチック、ガラス、鉄くずなどが含まれます。解体工事業者に残置物の処分を依頼した場合、同じ残置物でも産業廃棄物として扱われるようになります。
特徴:
産業廃棄物は廃棄物処理法の規定に則って、中間処理施設や最終処分場などの決められた場所で処分しなければなりません。そのため、一般廃棄物として処分するよりも費用が大幅に高くなります。また、産業廃棄物の収集運搬や処分には、都道府県知事から許可を受けた「産業廃棄物収集運搬業」の営業許可が必要です。
具体例
解体工事で発生する木材、屋根瓦、石膏ボード、コンクリート片などが挙げられます。
家電4品目とパソコンの特殊な扱い
特定の電化製品は、上記とは異なる特別な処分方法が法律で定められています。
- 家電4品目: エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫(冷凍庫)、洗濯機(衣類乾燥機)の4つを指し、家電リサイクル法の対象品目です。これらは残置物と一緒に処分することができず、別途リサイクル料金と運搬費がかかります。
- パソコン: パソコンもまた、燃えるゴミや粗大ごみとして処分できません。PCリサイクルマークがあるものはメーカーに無料で引き取ってもらえます。
残置物は適切に処理しなければならない

残置物は適切に処理する必要があります。不適切な処理は、解体工事における重大な課題であり、単なる法律違反にとどまらない深刻な問題を引き起こします。
費用増加のリスク
残置物の処理を解体業者に依頼すると、別途費用が発生し、解体費用全体が高くなる傾向があります。
例えば、ベッドのスプリングマットレスを一般廃棄物の粗大ごみとして処分する場合、費用は約2,000円程度で済むのに対し、産業廃棄物として処分すると約5,000円もかかることがあります。
また、解体工事における残置物撤去費用は一軒家で20万円〜50万円程度、マンション・アパートで3万円〜30万円程度が相場ですが、大量のゴミが残された「ゴミ屋敷」のような状態では、100万円以上かかることもあります。
荷物の量や種類、整理されていない状態、エレベーターのない高層階や狭い道路などの立地、さらには「週末に対応してほしい」といった緊急性によっても残置物関連費用は大きく変動します。
しかし、これらの処理を施主自らが行えば、費用を大幅に削減することが可能です。
工期遅延の可能性
残置物が残ったままでは、解体工事の前にそれらを処分する必要があるため、工事の開始が遅れ、全体の工期が延びる可能性があります。これは、人件費の増加にもつながり、ひいては解体工事の費用を押し上げる要因となります。
残置物絡みの法的リスクと罰則
廃棄物処理法に基づき、解体工事の関係者には残置物の適切な分別・運搬・処分が義務付けられています。これを怠ると、不法投棄と見なされ、厳しい罰則が科される可能性があります。
多額の罰金や業務停止命令:
不法投棄が発覚すれば、事業者には行政からの改善命令や業務停止命令が下され、事業継続そのものが難しくなる可能性があります。
元請業者への責任追及
元請企業が下請業者に廃棄物処理を委託していた場合でも、監督責任や選任責任が問われ、元請自体が行政処分を受ける可能性があります。
環境への悪影響と社会問題
不法投棄は、山林や河川敷、空き地などの公共・私有地に廃棄物を無断で投棄する行為であり、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼすだけでなく、地域全体の景観や安全にも深刻なダメージを与えます。
近年、環境保護意識の高まりとともに、このような違法行為に対する社会の目は一段と厳しくなっており、行政による監視体制も強化されていますが、数か月おきに不法投棄のニュースが流れてくるのが現状です。
処理責任の不明確さ
建築物の解体時等に建築物の所有者や占有者等が残置した廃棄物の処理責任は建築物の所有者等にあります。
一方で、解体工事を請け負った元請業者が排出者として残置物を処理することは法律上できません。この処理責任の所在が不明確であることも、トラブルの原因となります。
残置物トラブルの原因
残置物の不適切な処理やトラブルが発生する背景には、いくつかの根本的な原因が存在します。
複雑な廃棄物分類と処理区分の誤解
残置物は、誰が処分するかによって「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類が変わり、それぞれ処理方法が異なります。
- 自分で処分する場合は一般廃棄物として扱われる一方、解体業者に依頼すると、同じ残置物でも産業廃棄物として扱われるようになります。
- 布団や衣類、不燃ゴミなどの「一般廃棄物」の処理を解体工事業者が行うことは法律上できません。解体業者が対応する場合、外部の専門業者に委託することになり、その分費用が高くつきます。この複雑な区分が、所有者の混乱を招く一因です。
情報不足と認識の低さ
建築物の解体等を行う際には、建築物の所有者等が、工事の着手前に残置物を適正に処理する必要があるにもかかわらず、その認識が不足している場合があります。
残置物が多量に残されていると、解体工事中に想定外の残置物が見つかり、予算を超える追加費用が発生するケースがあります。これは施主、業者ともに事前の残置物確認が不十分であることが原因です。
事前確認とコミュニケーション不足
処理方法や費用について、施工業者と施主の間で情報の共有が不足していると、後から「こんなに費用がかかるとは思わなかった」という不満が生じることがあります。
事前に残置物についての共通認識を作っておくことが重要であり、日本クレストでは見積り時にしっかりと残置物の処分についても打ち合わせをさせていただいております。
具体的な解決策

残置物問題による費用増加やトラブルを回避し、解体工事を円滑に進めるためには、以下の具体的なアクションプランを実行することが重要です。
所有者自身による事前の残置物処分を徹底する
残置物の撤去費用を抑える最も効果的な方法は、解体工事が始まる前にできる限り自分で処分しておくことです。自分で処分すれば一般廃棄物として扱われるため、業者に依頼するよりも安く処分できます。
- 可燃ごみ・不燃ごみ: 雑誌、新聞、衣類、プラスチック製品、小物などは自治体のゴミ収集サービスを利用し、無料で処分しましょう。
- 粗大ごみ: 小さな家具や家電(椅子、テーブル、布団など)は、自治体の粗大ごみ回収システムを利用することで、数百円〜数千円程度の負担で処分可能です。
※予約やシール購入が必要な場合あり - 家電4品目とパソコン: エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象であり、別途リサイクル料金と運搬費がかかります。パソコンも同様にメーカー回収や専門業者を利用しましょう。PCリサイクルマークがあるパソコンは、メーカーに無料で引き取ってもらえます。
- 使えるものの再利用: まだ使える家具や家電は、リサイクルショップへの持ち込み、フリマサイト(例:メルカリ、ジモティーなど)への出品、または知人や地域の掲示板で譲ることを検討しましょう。これは費用の削減だけでなく、廃棄物の削減=環境配慮にもつながります。
信頼できる専門業者を選定し、適切な契約を結ぶ
自分で処分しきれない残置物や産業廃棄物の処理は、専門業者に依頼することになります。この際、信頼できる業者を選ぶことが極めて重要です。
「産業廃棄物収集運搬業」の許可を確認
残置物の運搬には「産業廃棄物収集運搬業」の営業許可が必要です。解体業者に依頼する際は、その業者が収集運搬業の許可を得た正規業者であることを確認しましょう。

当社は岡山、広島、兵庫の収集運搬許可を持っています。
⇒https://www.japan-crest.co.jp/aboutus/
相見積もりの取得
残置物の撤去費用は業者によって数万円単位で差が出ることがあるため、複数の業者から見積もりを取って比較することが重要です。
現地での見積もりと内訳確認
電話やメールだけでなく、現地での立ち会い見積もりを依頼し、作業内容と費用を明確にすることがトラブル回避につながります。見積書には「作業費」「処分費」「人件費」「車両費」などの詳細な内訳が記載されているかを確認し、「一式〇万円」といった曖昧な見積もりは避けましょう。
マニフェスト制度の活用
産業廃棄物の排出事業者は、マニフェスト制度により廃棄物の種類・量・処分先を記録し、最終処分まで責任を持って管理する必要があります。業者の運用状況も確認し、透明性を確保することで不法投棄などの思わぬリスクを減らせます。
コミュニケーションの徹底
施工前に詳細な打ち合わせを行い、費用、作業内容、スケジュールを明確にすることが重要です。残置物リストを作成し、何が残されているかを明確にすることも、誤解を防ぐ上で有効です。
まとめ
以上、ご紹介したように、住宅等の解体工事で発生する残置物は、適切な事前準備と、信頼できる専門業者との連携が不可欠です。
残置物をできる限り施主自身が処分することで、廃棄物の処理費用や工期短縮による人件費の削減などが可能になり、費用負担を大幅に削減することが可能になります。
また、業者に依頼する際は、産業廃棄物収集運搬業の許可の有無、詳細な見積もり内容、そして過去の実績をしっかりと確認し、信頼できる業者を選ぶことが何よりも重要です。
これらの対策を講じることで、あなたは不必要なコストやトラブルを避け、安心して解体工事を進めることができるでしょう。そして、これは資源の有効活用や環境保護にも貢献する、社会的に責任ある行動にも繋がります。