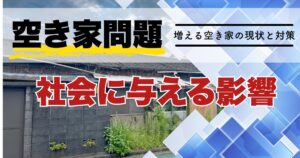空き家問題と政府の対策──所有者が今すぐ知っておくべきこと

日本ではいま、空き家の増加が社会問題となっています。
総務省の「住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家数は約900万戸を超え、住宅全体の13%以上が使われていません。
このままでは、老朽化した空き家の倒壊リスクや、放置による景観悪化、防犯・防災上の問題がますます深刻化すると懸念されています。
一方で、政府は空き家対策を「個人の問題」ではなく社会全体の課題と位置づけ、法整備や補助制度を拡充しています。
本記事では、その政府の対策の全体像と、所有者が具体的に取れる行動を詳しく解説します。
参考ページ
政府が動いた背景:空き家の増加がもたらすリスク
空き家が増える最大の要因は、人口減少と高齢化です。
特に地方では、親世代が亡くなっても相続された家が使われず、放置されるケースが増えています。
しかし、空き家をそのままにしておくと次のような問題が発生します。
- 屋根や外壁の崩落による通行人への危険
- 雑草・害虫・動物による衛生環境の悪化
- 放火・不法侵入などの防犯リスク
- 周辺地価への悪影響、地域全体の景観悪化
これらの問題があちこちで顕在化するとなると、それはもはや「個人の問題」ではなく、地域社会全体の安全や生活環境に関わる問題として扱われる、ということです。
政府の主な対策①:空き家対策特別措置法
政府が本格的に空き家対策に乗り出したのは、2015年施行の「空き家対策特別措置法」からです。
この法律では、放置された空き家を「特定空き家」に指定し、自治体が指導・勧告・命令を行えるようになりました。
特定空き家に指定される条件
- 倒壊などの危険がある
- ごみや雑草で衛生上問題がある
- 管理が不十分で景観を損なっている
- 近隣の生活環境に悪影響を与えている
指定されると、固定資産税の優遇措置が解除され、税負担が最大で6倍になることもあります。
つまり、「放置しておくほど損をする」仕組みになっているのです。
政府の主な対策②:空き家の活用支援と補助金制度
政府や自治体は、単に「取り壊せ」と命じるだけではなく、活用を促す仕組みも整えています。
主な支援例
- 空き家改修補助金
自治体によっては、リフォームや耐震改修の費用の一部を助成。 - 空き家バンク制度
空き家の所有者と、利用希望者(移住者・事業者など)をマッチング。 - 相続登記の義務化(2024年施行)
相続後3年以内の登記を義務づけ、所有者不明土地を減らす。 - 税制優遇(譲渡所得の特別控除)
相続した空き家を売却する際、最大3,000万円の特別控除が適用される制度も。
こうした制度を活用すれば、放置よりも活用・売却のほうが得策だという判断になります。
政府の主な対策③:地域と連携した空き家管理の強化
近年では、自治体が地元の建設業者やNPO法人と連携して、「空き家管理サービス」を提供する動きも広がっています。
定期的な見回りや清掃、通気・通水などの「簡易管理」を行政がサポートし、倒壊や不法侵入の予防につなげています。
また、「所有者不明土地等問題対策推進本部(内閣府)」が中心となり、全国的にデータベース化も進んでいます。
これにより、空き家の所在・所有者情報を共有し、活用促進のスピードを高めています。
所有者が取るべき実践的な対策
空き家問題を「自分ごと」として動くことが、最も効果的な対策です。
政府の制度を理解したうえで、次のような行動を取るとよいでしょう。
- 現状の確認と管理計画を立てる
年に数回は現地を確認し、老朽化や雑草、屋根の破損などをチェック。 - 行政の支援窓口に相談する
各市町村には「空き家対策課」「空き家バンク」などの専門部署があります。 - 専門業者に調査・見積りを依頼する
解体・改修・売却など、次のステップを決めるための基礎資料になります。 - 将来的な活用を考える
賃貸、民泊、店舗リノベーションなど、活用の方向性を早めに検討。
まとめ:政府の動きを知り、放置から「活用」へ
「空き家問題 対策 政府」というキーワードが示すように、
今や国レベルで空き家の管理・活用を促す時代になっています。
放置は税金・リスク・近隣トラブルを招くだけでなく、
相続や売却の際にも大きな負担になります。
一方で、政府の補助制度や空き家バンクを上手に活用すれば、
「負の資産」を「地域に貢献できる資産」に変えることも可能です。
まずは、自治体の窓口や公式サイトを確認し、
あなたの空き家に使える支援制度がないか探してみましょう。