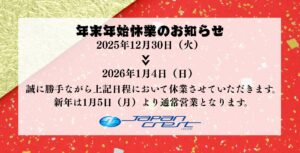空き家問題とビジネス:社会課題を新たなチャンスに変える最新活用術

日本の空き家は900万戸を超え、社会課題として大きく取り上げられる一方、その裏側には新たなビジネスチャンスが急速に広がっています。
解体・リノベーション・管理・売買・体験型施設など、多様なプレーヤーが参入し、市場規模は最大9兆円と推計されるほど拡大中です。
かつて「負動産」とされていた空き家の中には、再生・利活用によって地域と経済を動かす重要な資源へと変わりつつあるものもあります。本記事では、空き家ビジネスの最新動向と可能性をわかりやすく紹介します。
こちらもおすすめ
TBSがっちりマンデーでも取り上げられた空き家ビジネス
TBSの人気番組「がっちりマンデー!!」でも過去特集されたように、空き家は“社会問題”である一方、捉え方次第では大きなビジネスチャンスにもなっています。空き家そのものに価値がないのではなく、「再生の仕方」「出口の作り方」によって利益を生み出せる点がポイントです。番組で過去に紹介された企業を見ると、空き家ビジネスには次のような多様な視点があることがわかります。
- ジェクトワン(アキサポ)
空き家を所有者から借り上げ、リノベーション費用を自社負担で実施。その後、店舗・賃貸・シェアスペースなどに再生して収益化する“借上げ再生モデル”。ただし老朽化が進んでいる、立地が悪い場合には利用が難しい場合も。 - 山翠舎(古材再利用)
古民家を解体し、150〜200年前の梁や柱を洗浄・加工して高値で販売。捨てられるはずの古材を“宝の山”へと変えるサーキュラー型のモデル。歴史的価値のあるものが対象なので築40〜60年の一般的な住宅は対象外。 - カチタス(買取再販モデル)
空き家や古い戸建てを買い取り、リフォーム後に再販売。地方の低価格住宅に特化した“買取→再生→販売”というスピード感のあるビジネス。こちらも老朽化が進んでいたり、立地上再販が難しそうな場合は対象外となるケースも。
これらの共通点は、空き家の課題(老朽化・維持費・需要の低さ)を“再生と転用”で価値に変えていること。
活用方法は「貸す」「売る」「素材を活かす」など多岐にわたり、空き家問題を逆手に取った新しい市場が広がっています。
その他にもある空き家ビジネスのベンチャー企業
空き家市場は年々プレイヤーが増えており、大手だけでなくスタートアップや地域系ベンチャーも独自のサービスを展開しています。彼らの多くは、「空き家を負債ではなく資源へ」という共通の視点で、IT・マッチング・サブスク・リノベーションなど多様な切り口から課題解決を図っています。ここでは代表的な企業とサービス内容を、短くわかりやすくまとめます。
- 株式会社アドレス(ADDress)
全国の空き家を“住み放題のサブスク”として展開。月定額で複数拠点に住める新しい生活スタイルを提供。 - 株式会社WAKUWAKU(Renottaなど)
デザインリノベーションブランドを展開。空き家や空室物件を“おしゃれに再生”し、賃貸価値を向上させる。 - 空き家活用株式会社(空き家活用LABO)
空き家の調査・分析から、利活用プラン、収益化モデルの提案まで一気通貫。自治体との連携も多い。 - 家いちば株式会社
売主と買主が直接出会える「空き家のフリマ」を提供。築古物件でもそのまま“現状渡し”で売れるのが強み。 - 株式会社L&F
放置空き家の管理・巡回・清掃を代行。所有者が遠方でも安心できる“空き家見守りサービス”を提供。 - リノべる株式会社(リノベる。)
中古住宅+リノベーションの総合サービス。空き家を“理想の住まい”に再生し、若年層の購入需要に対応。 - クラッソーネ
解体工事の一括見積もりサービス。空き家除却を希望する所有者と、解体業者をマッチングし課題を解決。 - リノバンク(RenoBank)
空き家や中古戸建てについて、「活用できるか」「いくらくらいで流通しそうか」をオンライン診断し、リノベ前提の売買・活用を支援する“空き家DX×リノベ流通”モデル。
こうしたベンチャーの登場により、空き家活用は「リノベ」「売買」「管理」「サブスク」「解体」「融資」など、あらゆる角度からビジネス化が進んでいます。空き家問題は単なる老朽化の問題ではなく、サービスを組み合わせることで新しい価値を生むフィールドへと進化しています。
空き家ビジネス×田舎

地方の空き家は、都市部とは違った形でビジネスチャンスがあり、人口減少で放置されがちな古民家や空き家を「地域資源」として再生する動きが全国で広がっています。
たとえば、古民家をリノベーションして宿泊施設にするケースは増えており、観光目的だけでなく「田舎暮らし体験」や「移住希望者のお試し住宅」としてのニーズも高まっています。
また、農業体験や収穫イベントなどの体験型農園(アグリツーリズム)も注目されており、空き家を拠点にして小規模から始められる点が大きな魅力です。さらに、ワーケーション需要の高まりによって、田舎の空き家をサテライトオフィスとして利用する企業も増加中です。低コストで拠点を構えられ、地域との交流も生まれやすいというメリットがあります。
空き家周辺の広い土地や日当たりの良さを生かし、太陽光発電事業へと変える事例もあります。まとめると、田舎の空き家から生まれる主なビジネスアイデアは以下の通りです。
- 古民家宿・田舎暮らし体験施設
- 農業体験・アグリツーリズム拠点
- サテライトオフィス・ワーケーション施設
- 太陽光発電・エネルギー活用モデル
田舎の空き家は“負動産”として放置されがちですが、活用次第で地域と外部人材をつなぐ重要なハブへと変わる可能性を秘めています。
空き家ビジネスに使える補助金
空き家ビジネスを始める際には、国や自治体が用意している 補助金制度を上手く活用することが大きな後押し になります。活用方法によっては、リノベーション費用や解体費、空き家取得費などを軽減でき、新規事業の立ち上げリスクを抑えることが可能です。代表的な補助金としては、次のようなものがあります。
- 小規模事業者持続化補助金
空き家を活用して宿泊施設・カフェ・サテライトオフィスなどの新規事業を始める際に利用可能。改修費や広告費など幅広い経費が対象。 - 空き家対策総合支援事業(国交省)
自治体を通じて、空き家の解体・修繕・活用などに補助が出る制度。老朽空き家の除却や、利活用のための改修工事が対象になる場合があります。 - 自治体独自の空き家活用補助金
名古屋市・京都市など多くの自治体が、改修費・仲介手数料補助・解体費補助など独自制度を設けています。用途を「滞在施設・交流拠点・創作活動スペース」などに限定している地域もあります。
なお、補助金には、
- 事前申請が必須
- 年度予算枠があり早期締切の可能性
- 用途・築年数・空家期間など細かい条件
といった注意点もあります。空き家の再生は初期投資が重くなりがちですが、補助金を組み合わせることで費用負担を抑え、ビジネスとして成立しやすくなります。
空き家ビジネスに資格は必要?
空き家ビジネスは、実は 必ずしも資格が必要というわけではありません。
所有している空き家をリノベーションして、宿泊施設や賃貸、サテライトオフィスとして活用する場合などは、国家資格がなくても始められるケースが多く、「空き家管理サービス」も巡回・清掃・簡易補修であれば資格不要です。
一方で、ビジネスモデルによっては資格や許可が必要になります。
例えば、他人の空き家を売買・仲介する場合には 宅地建物取引士(宅建士) が関わりますし、大規模な改修や用途変更を行うなら、建築士や施工管理技士、建築基準法・消防法の届出が必要です。また、宿泊施設として運営する場合は 旅館業法や住宅宿泊事業法(民泊) の許可が欠かせません。
つまり空き家ビジネスは、“何をするか” によって必要な資格が変わるのがポイント。
事業範囲を明確にすることで無資格でも始められる領域は十分にあります。
空き家ビジネスの市場規模
近年、空き家の増加にともなって「空き家ビジネス」の市場は急速に存在感を高めています。
総務省 統計局によれば、2023年時点で日本の空き家は 約900万戸 に達し、住宅全体の 約14% を占める水準となっています。これは人口減少・高齢化の進行により、今後も増加することが確実視されている領域です。
また、リフォーム産業新聞社のプレスリリースによれば、空き家に関連するビジネスの潜在市場規模は、約9兆601億円 と試算されており、その内訳は
- 中古住宅流通:約6兆4,069億円
- リフォーム:約1兆727億円
- 解体・撤去:約4,150億円
など、多岐にわたります。
一方で、空き家ビズが公表する別の推計では、市場規模を 約4兆円 と見込むデータもあり、試算方法により幅があるのが現状です。また、「空き家管理」だけに絞ると、現在の市場は 約500億円、2030年には 約1,500億円規模 に成長するとの予測もあります。
これらの数字から言えるのは、「空き家問題=社会課題」でありながら、
- 解体・撤去
- リフォーム・再生
- 管理サービス
- 買取再販
など、多様な分野でビジネスチャンスが広がっているということです。
ただし、9兆円の潜在市場はあくまで“理論値”であり、実際に収益化されている市場はもっと小さいと言われています。参入するには物件の状態・立地・需要・用途転換の可能性などの見極めが不可欠です。
まとめ
空き家は放置すれば老朽化や治安悪化を招く課題ですが、視点を変えれば「再生」「利活用」「再販」など、多彩なビジネスに発展する大きな可能性を秘めています。
補助金の活用や適切な資格取得により参入ハードルは下げられ、都市部・地方のいずれでも新たな価値を創出できます。
空き家問題は社会の重荷ではなく、地域活性化や経済循環を生み出すフィールドへと変化しています。需要の伸びる今こそ、事業者にとって最も追い風の強いタイミングです。
《こちらもおすすめ》