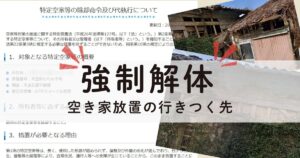相続登記の義務化とは?2024年4月からスタートした新制度をわかりやすく解説
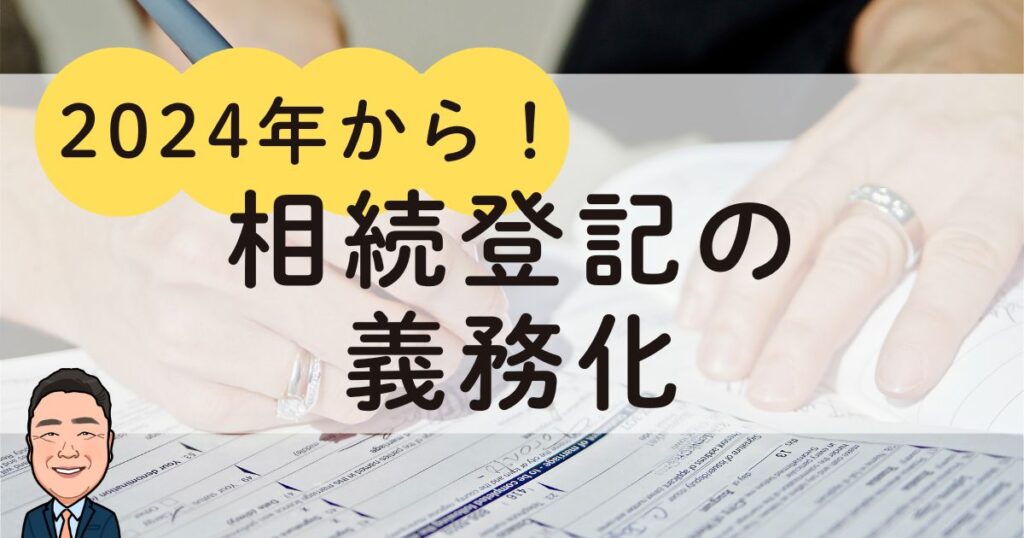
全国で空き家や所有者不明土地の増加が問題となる中、2024年(令和6年)4月から「相続登記の義務化」が始まりました。
これまで任意だった登記申請が法律上の義務となり、相続した不動産を放置しておくと過料(罰金)が科される可能性があります。
なぜ相続登記が義務化されたのか
少し前までの日本では、親や祖父母が亡くなっても相続登記をせずに放置されるケースが多くありました。特に資産価値のない不動産などは相続しても負担ばかりが増えるだけです。意識が向けられることも少なく、相続の手続きが取られないままになってしまいがちだったのです。
その結果、子、孫へと代替わりするうちに相続人が10人以上に分かれてしまうケースも珍しくない状況となるのです。
所有者が特定できない土地は、売却・賃貸・公共事業・災害復旧など、あらゆる場面で障害になります。
こうした「所有者不明土地問題」に歯止めをかけるために導入されたのが、相続登記の義務化です。
義務化の内容と罰則
法律(改正不動産登記法)により、次のように定められています。
- 施行日:2024年(令和6年)4月1日
- 対象:相続などで土地・建物を取得した人
- 期限:相続があったことを知った日から3年以内に登記申請を行うこと
- 罰則:正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料(行政罰)
つまり、これまでのように「時間があるときにやろう」と後回しにすることが法律違反となる可能性があるということです。上記の通り、罰則まで課される可能性があります。
放置するとどうなる?
登記をしないまま放置すると、相続人が増えるたびに手続きが複雑になり、最終的には誰も管理できない土地や家になってしまう恐れがあります。
岡山や倉敷でも、こうした「所有者不明の空き家」が問題化しており、行政が撤去を進めたくても所有者を特定できず、作業が止まる事例が増えています。
相続登記を早めに行うメリット
- 不動産の売却や解体、利活用がスムーズになる
- 名義を明確にして相続トラブルを防止できる
- 将来的に発生する税金・補助金の手続きが簡単になる
早めの登記は、家族の負担を減らし、空き家の放置リスクを防ぐ第一歩です。